JUST KEEP BUYING
本書冒頭にもあるがこれは自動的に富が増え続ける「3語の呪文」です。
YouTubeや書籍でお金の勉強をしている方であれば一度は聞いたことがあるかもしれません。
この本では、S&P500に連動するインデックスファンドをただひたすらに買い続けること
(ドルコスト平均法)が最強の投資方法であることを過去のデータをもとに
分かりやすく解説してくれています。
しかしただの投資バイブルであるだけでなく、人生における成功の秘訣も教えてくれる書籍でした。
その成功の秘訣とは、小さなことをただ愚直に続けていくこと(JUST KEEP ⚪︎⚪︎ING)が大きな目標へ到達するための唯一の道であるということです。
冒頭でYouTubeで成功を収めた方が守っていたルールがJUST KEEP UPLOADING
(とにかく動画を投稿し続けなさい)であることに触れています。
本書は以下のような2部構成となっております
- 貯金力アップ編
お金を貯める基礎体力を身につける。収入と支出を管理し、無駄を見直すことで投資の準備が整います。 - 投資力アップ編
お金を「働かせる」力を養う。収入が増えれば支出も増えるとは限りません。増えたお金を資産へと変える思考が重要です。
これら2つの力を合わせることで資産を形成するための法則を学べました。
本書は全20章で構成されていますが、その中でも特に印象に残ったものが以下になります。
- 第3章 こうすればもっと貯金できる – パーソナルファイナンス最大のウソ
- 第12章 個別株は買うな – 個人投資家を焼き尽くす投資哲学
以下で詳しく解説します。
第3章 こうすればもっと貯金できる – パーソナルファイナンス最大のウソ
お金持ちになるために必要なこと、それは”収入を増やし、収益を生み出す資産に投資”することとあります。無駄な支出を減らすことも大切だが、限界もあります。
収入を増やすことは青天井であります。本書では収入を増やす方法についても触れており、主に以下の5つとなっております。
- 時間単位の専門サービスを提供する
例:コンサル、デザイナー、家庭教師など。自分のスキルを時給制で売る方法です。 - 出来高性の専門サービスを提供する
成果報酬型の仕事(営業、ライター、動画編集など)。働く量ではなく、結果で報酬が決まります。 - 人に教える
知識や経験を誰かに教えることで収入を得る。講師業、コーチング、オンライン講座など。 - 商品を売る
物理的な商品やデジタル商品など、自分のアイデアを「モノ」にして販売する方法です。 - 会社で昇進する
組織の中で評価され、役職や報酬を上げていくオーソドックスな方法。
どれにもメリット・デメリットがありますし、向き不向きもあります。
だからこそ、自分のスキルや性格、環境に合わせて試してみることが大切です。
ただし、これらの方法はあくまで収入を増やすための“手段”であり、“最終ゴール”ではないという点にも注目です。
本書が提唱する「究極の形」は、オーナーシップを持つことです。
自分が築いた資産を活用して、さらに資産を増やしていく――。
働く時間や労力ではなく、「お金や仕組み」に働かせる側に回ることが、本当の意味での富を築く道なのです。
自分にとっての「ちょうどいい豊かさ」を考える
本書では、「オーナーシップを持つことが最も富を築く道である」と述べられています。
たしかにそれはひとつの理想の形ですし、目指す価値のあるゴールだと思います。
でも、僕はそれ以上に大切なのは、「自分がどんな生き方をしたいのか」を考えることだと思っています。
その理想の暮らしには、いくら必要なのか? それを逆算していく視点も欠かせません。
僕自身の目標は、「30代で5,000万円の資産を築いて、サイドFIRE(経済的自立+ゆるく働く生活)」を実現することです。
この目標においては、必ずしもオーナーシップ(資産の仕組みを持つこと)を持つ必要はないと感じています。
むしろ、たとえば会社員として働きながら(5. 昇進)、それに加えて自分のスキルを活かして
副業(1〜4)を行い、余剰資金をインデックスファンドにコツコツ投資していく――。
そんな“無理のない範囲で小金持ちを目指す”ライフスタイルも、現実的で魅力的ではないでしょうか?
第12章 個別株は買うな – 個人投資家を焼き尽くす投資哲学
理由は以下の2つである。順に説明します。
- 多くのアクティブ運用はインデックス運用にか勝てない
- 銘柄選びがうまくできているかわからない
多くのアクティブ運用はインデックス運用にか勝てない
■ インデックス運用
インデックス運用とは、日経平均やS&P500など、市場全体の動きを示す「指数(インデックス)」に連動するように資産を運用する方法です。
市場全体に投資するイメージで、手間も少なく、長期投資向きのスタイルです。
■ アクティブ運用
一方のアクティブ運用は、個別株などを選んで、インデックス運用よりも高いリターン(利益)を狙う方法です。
ファンドマネージャーや投資家自身が積極的に銘柄を選定・売買して運用します。
では、実際のところどちらがうまくいっているのでしょうか?
ある5年間の分析によると、アクティブファンドの約75%が、ベンチマーク(比較対象となる市場指数)を上回ることができなかったというデータがあります。
つまり、多くのプロが市場平均にすら勝てていないのです。
さらに、アメリカの株式市場の歴史を見ても、「長年にわたって市場で生き残り続けている銘柄」はごくわずか。
企業の栄枯盛衰が激しい株式市場で、長期的に“当たり”を引き続けるのは極めて難しいという現実があります。
これらのデータが示しているのは、「市場に勝つことの難しさ」、そして「勝ち続けることのほぼ不可能さ」です。
プロですら苦戦しているのに、僕たちのような一般の個人投資家が市場を上回るリターンを狙うのは、はっきり言って無謀です。
だからこそ、インデックスファンドを購入して長期保有する、というシンプルな戦略が最も合理的なのです。
市場に勝とうとするのではなく、市場と共に成長する。
それが、株式投資で成功するための王道であり、最も再現性の高い方法と言えるでしょう。
銘柄選びがうまくできているかわからない
アクティブ運用は、初心者にとって精神的な負担が大きい投資スタイルです。
なぜなら、常に「判断」を求められるからです。
スポーツの世界では、試合を見ればその人の実力は一目瞭然ですよね。
でも株式投資の世界では、そう簡単には実力が見えません。
たとえば、ある個別株を買って大きく値上がりしたとしましょう。
「自分の分析が当たった!」と思うかもしれませんが、実際にはたまたま好材料が出た、全体相場が上がったなど、自分とは無関係な要因が影響していることも多いのです。
逆に、株価が下がったときには「買い増しするべきか? それとも損切りするべきか?」と悩むことになります。
この“判断疲れ”が積み重なることで、投資がどんどんストレスになっていきます。
さらに厄介なのは、「自分の投資判断が本当に正しかったのかどうか」が見えにくいこと。
スポーツのように明確な評価軸がないため、ずっと不安を抱えたままになりがちです。
だからこそ、初心者にはインデックス投資が向いています。
インデックスファンドであれば、買ったら基本的には“ほったらかし”でOK。
判断に時間を取られることもなく、メンタルにも優しい投資法です。
時間や労力、精神的な負担を抑えつつ、長期的に資産を増やしていける。
インデックス投資は、多くの人にとって現実的かつ再現性の高い選択肢なのです。
終わりに
今回はこの本の特に面白いと思った箇所を紹介しましたが、全20章のうちどれもデータを基に述べられているため納得できるものでした。
すでに投資をしている人にとっては、本書の内容が安心材料となり、これから投資を始めようと考えている人にとっては、疑問や不安を払拭してくれる“バイブル”のような存在になるでしょう。
とくに、次のような疑問を持っている方は多いのではないでしょうか?
- いつ投資を始めたらいいの?
- どのタイミングで買うのがおすすめ?
- 暴落が起きたらどうすればいいの?
こうした悩みに対して、本書は明確な答えを示してくれます。
だからこそ、投資初心者こそ読むべき一冊だと断言できます。
さらにこの本は、単なる投資のテクニックにとどまらず、お金との付き合い方や、時間の価値についても深く考えさせてくれます。
読み終えた後には、自分のお金の使い方や人生設計にも目が向くはずです。
僕自身、この本を繰り返し読むことで投資への不安が和らぎました。
とくに暴落時など、気持ちが揺れそうなときこそ、何度でも読み返してほしい一冊です。
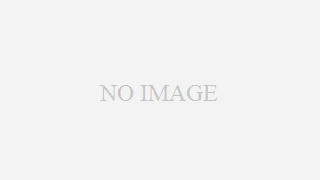

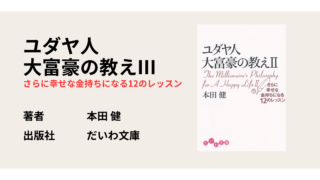

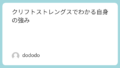
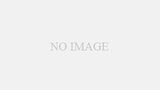
コメント